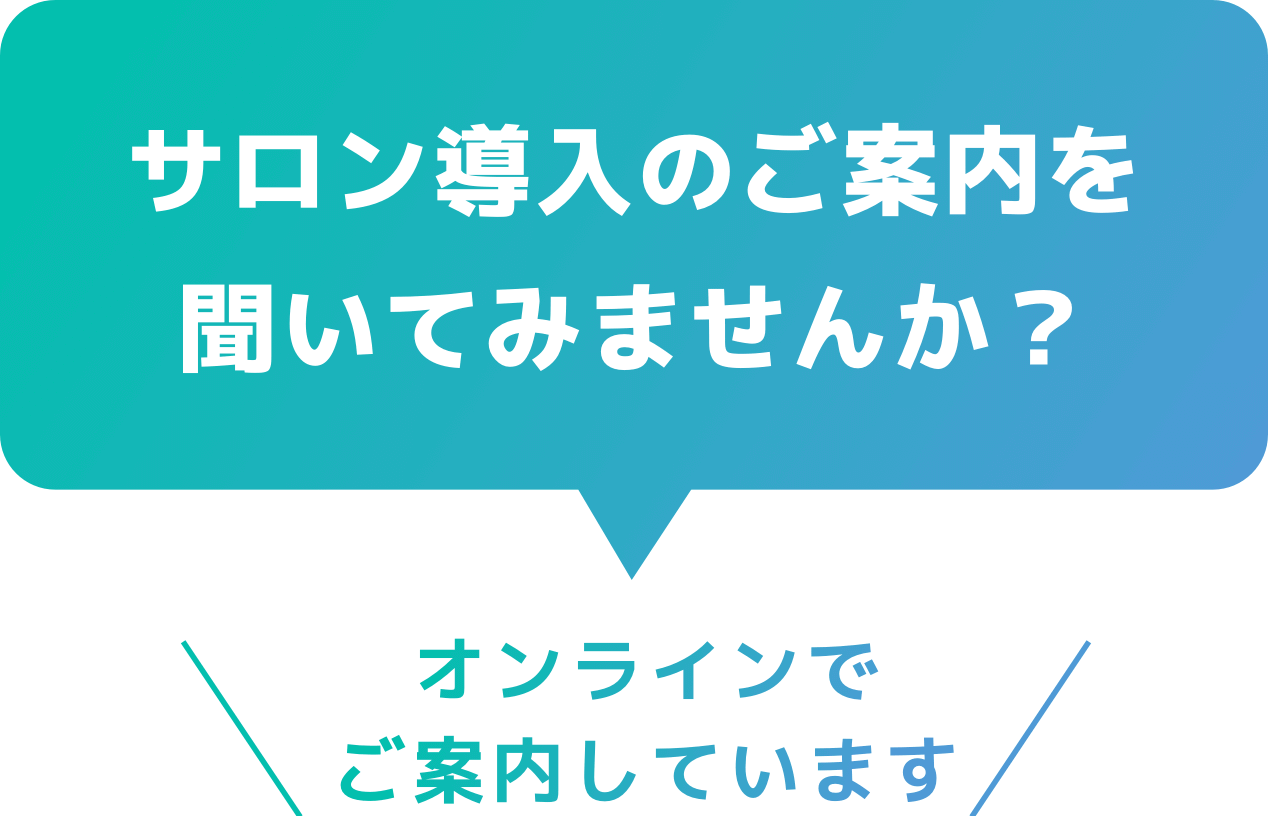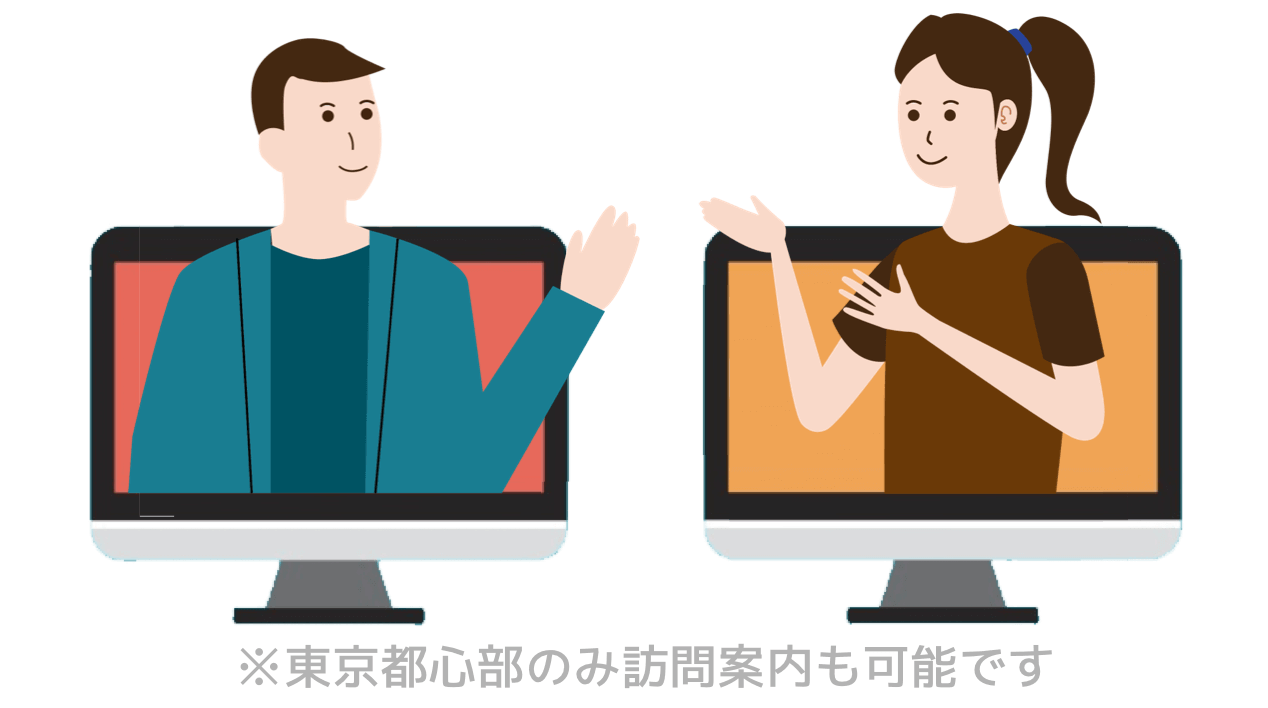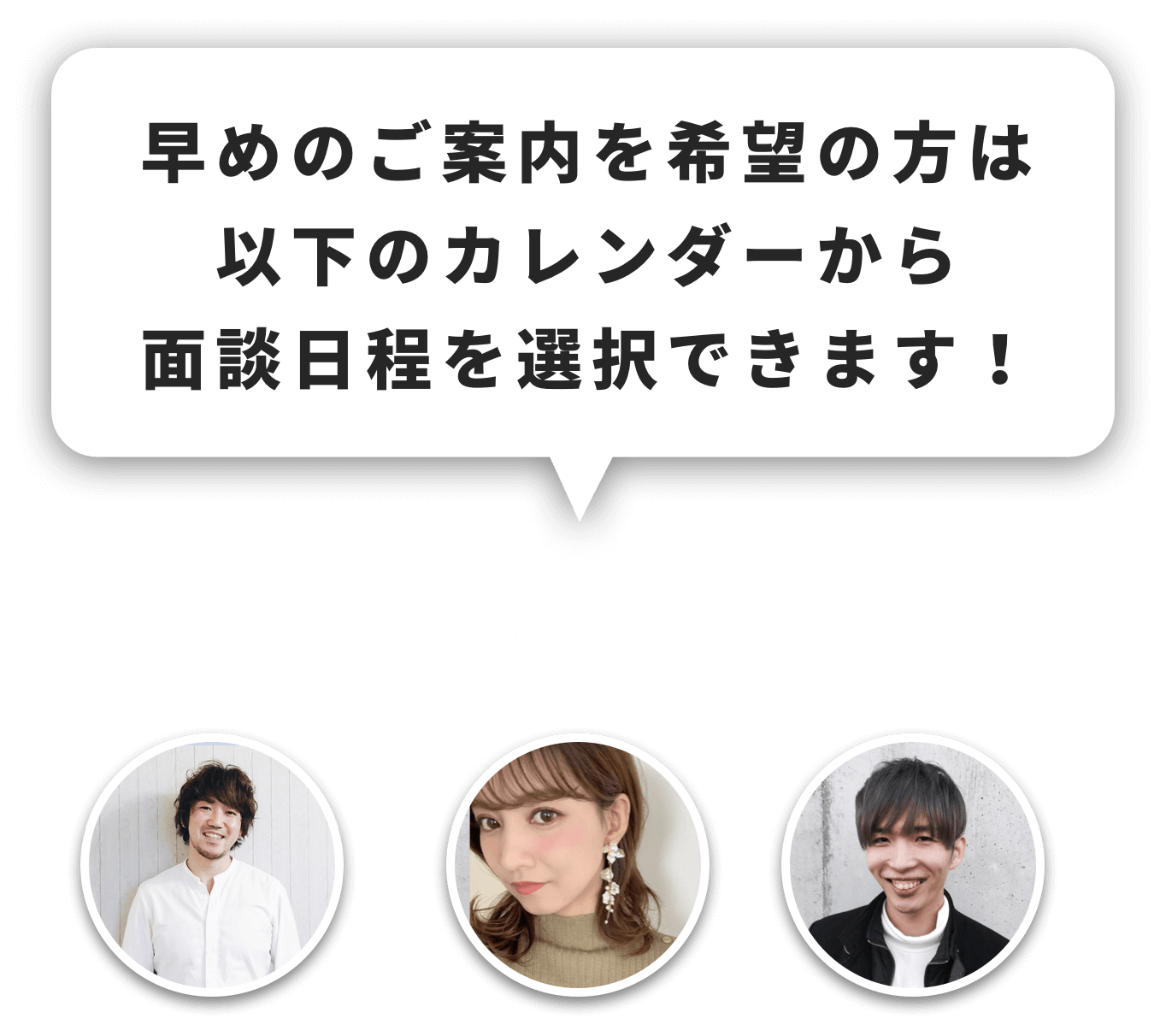【東京美容師物語】2液は過水でいいですか?
東京は表参道。
「日本一の美容師」を目指すアシスタントのかずやは、今日もチョコチップスティックパンで空腹をしのいでいた。
この物語は、かずやのまわりで巻き起こる笑いと涙の『美容師物語』である。

ピピピピッ、ピピピピッ、ピピピピッ、

iPhoneのアラームがAM8:00を知らせる。
保湿のためにつけていた綿の手袋は、いつのまにか手からはずれ床に転がっていた。
寝ている間に掻きむしっていたのか、10本の指はところどころ赤く出血している。
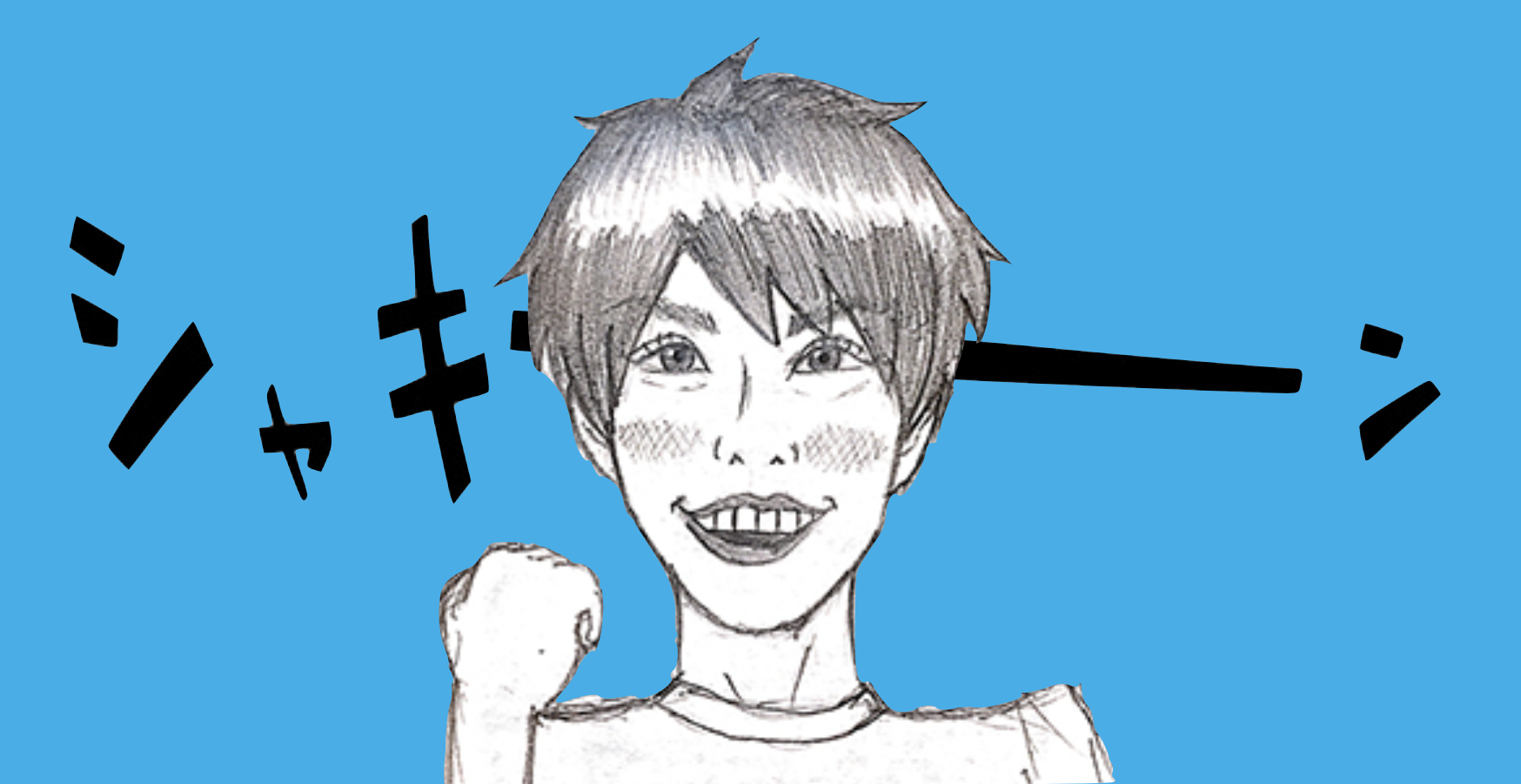
- かずや
- 美容師アシスタント3年目。日本一の美容師を目指し福岡から上京するも、持ち前の不器用さでシャンプー合格まで半年を費やす。ラーメンは細麺派。長男。
「また寝言いってたよ」
かずやに背を向ける形で布団にくるまっていた加奈が、そのままの体勢で不機嫌そうに言う。
「柴原さん、カラーチェックお願いします!…って」

土曜の美容室は戦場だ。
アシスタントリーダーのかずやにとって、この戦場をいかに円滑に回すかが重要なミッションになる。
PM5:30をまわり、サロンは少しずつ落ち着きをみせていた。
予約表とフロアの状況を確認し、今しかチャンスはないと判断した。
1段飛ばしで階段を駆け上がる。
勢いよくスタッフルームの扉を開けると、そこにはスタイリストの柴原の姿があった。

- 柴原修介
- いま最も勢いのある人気スタイリスト。デビュー初月に150万の売上を達成した記録保持者。情深く涙もろい。口癖は「お前ら、愛してるぜ〜」
 「おぅかずや、俺も食うぜ〜」
「おぅかずや、俺も食うぜ〜」
柴原が電気ケトルでお湯を沸かす。
 「きまってんだろ」
「きまってんだろ」


そんなんだから手荒れ治んねーんだよ」
かずやの両手の指はシワに沿っていくつもの赤切れができ、指先はカエルのように丸く膨れていた。
柴原の手は美容師とは思えないほど綺麗な状態を保っている。
柴原がチリトマトを食べようとフタに手をかけた、まさにその時だった…
「柴原さん、お客様ご来店です!」

1年目アシスタントがスタッフルームへ入るなり柴原へ告げた。
「◯◯様です!」
「なんか、早くいらしたみたいで…」
「あ…お、お待ちいただきますか?」
柴原は大きなため息をつき、ゆっくりと席を立った。

土日の柴原は多いときで20名もの顧客を担当する。
入社から1年2ヶ月でスタイリストデビューを果たし、デビュー初月に150万の売上を達成したことは今や伝説となっている。
かずやはそんな柴原に憧れ、彼のようなスタイリストになりたいと強く思っていた。
柴原の言動はお客様やスタッフへの「愛」に満ちている。
ときに厳しく、ときに優しく。

ブローの最中、顧客の女性は終始喋りつづけていたが柴原はただひたすら笑顔で頷いていた。
「そしたらぁ〜、その人が実は既婚者でぇ〜」
「そもそも既婚者のくせに合コン来んなよって感じじゃないですかぁ〜」
「柴原さんは彼女います〜?」
「美容師さんて客と付き合ったりするんですか〜?」
「まぁでも美容師さんチャラそうだからな〜」
かずやは柴原の笑顔の理由を知っていた。
ドライヤーの音にかき消され、話の内容を何一つ聞き取れずにただ笑っているだけだということを、、
その頃、柴原のカップヌードルはというと汁がなくなりうどん並の太さになっていた。
それを見たスタッフは口を揃えて「え…これ誰の?笑」と少し嬉しそうにしている。
柴原は本当にこれを食べる気なのだろうか?

忙しい土曜のサロンワークを終え、日付が変わる頃にかずやは家路に着いた。
毎週金土の夜は、彼女の加奈が泊まりにくる決まりだ。
OLとして働く加奈とはなかなか休みも合わず、こうして金土の夜にしか会うことはない。
まともなデートもできず申し訳ない気持ちもあるが、かずやにとってこの何でもない夜の時間が幸せだった。
一緒にお風呂に入り、色違いのスウェットを着て、録画したドラマを観ながら発泡酒で乾杯をする。
かずやが足を開きその間に加奈が体育座りをする格好が、いつものポジションだ。
下唇をつきだし両膝にアゴをのせてTV画面を見つめる加奈の姿。その横顔を後ろから眺めるのが好きだった。

ベッドの中でその日あった出来事を互いに話し、どちらからともなくキスをして、そのままだらだらとセックスをする。
かずやはすでに手荒れのケアを終え綿の手袋をはめていたので、愛撫はすべて口責めだ。
ピピピピッ、ピピピピッ、ピピピピッ、

iPhoneのアラームがAM8:00を知らせる。
保湿のためにつけていた綿の手袋は、いつのまにか手からはずれ床に転がっていた。
寝ている間に掻きむしっていたのか、10本の指はところどころ赤く出血している。
「また寝言いってたよ」
かずやに背を向ける形で布団にくるまっていた加奈が、そのままの体勢で不機嫌そうに言う。
「2液は過水でいいですか!?…って」
ー つづく ー